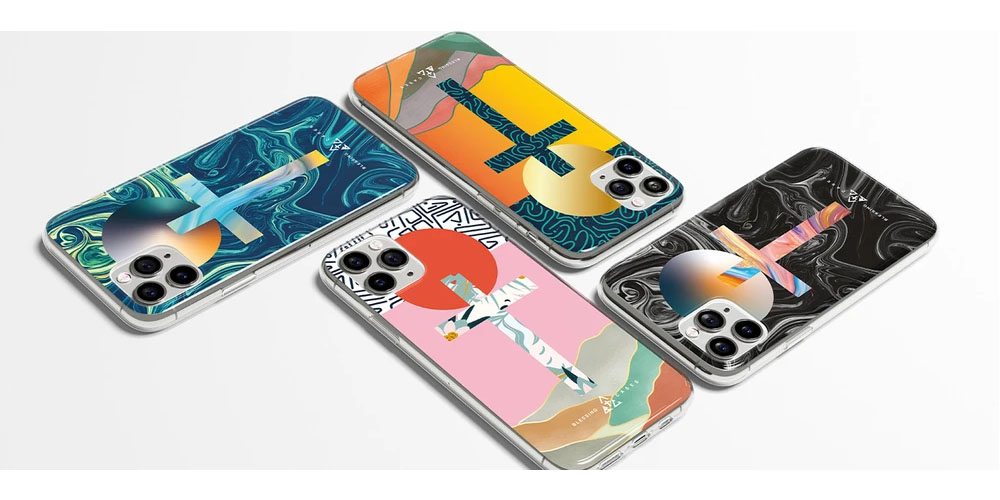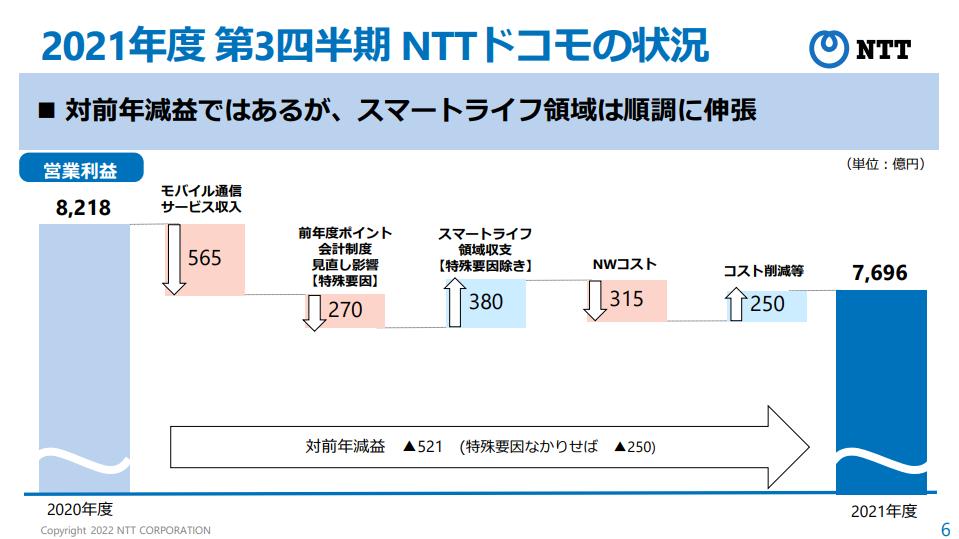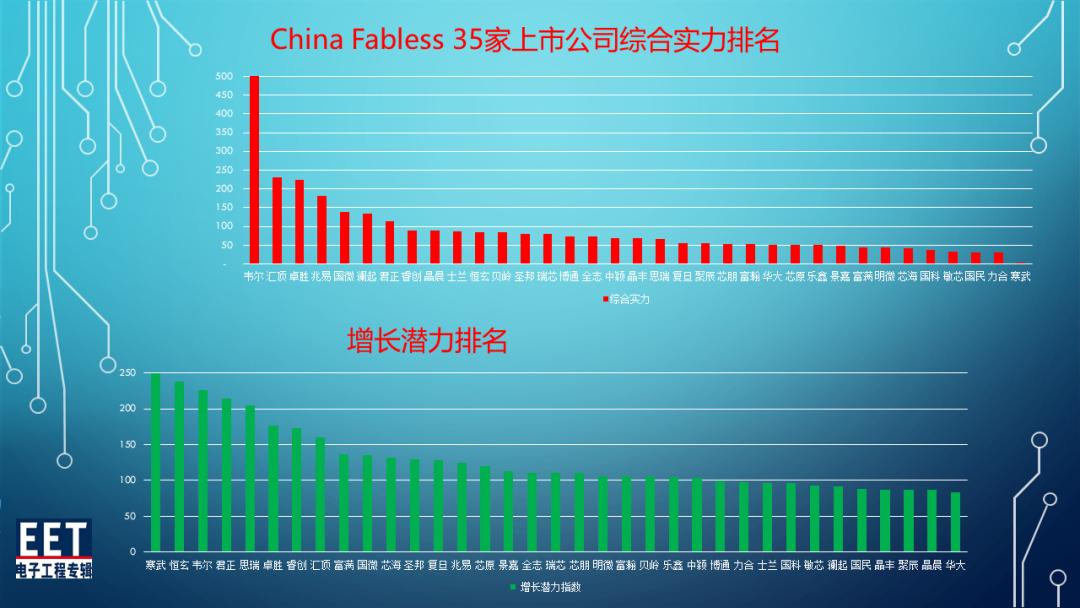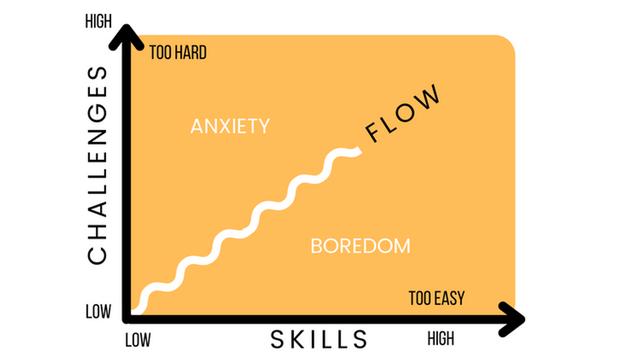【男の本音】「子どもが欲しい」という気持ちに気づいた瞬間のこと
子どもの頃の私(『ESQUIRE』US版の副編集長ベン・ボスコヴィッチ)は、何かあればすぐに泣くような子でした。なぜなら、周りの人たちは皆、自分にマイナスの烙印を押しているに違いない、と思えてならなかったからです。
そんなわけで、簡単なことですぐに泣いてしまう自分のことを、私自身が一番許せずにいました。両親もクラスメートも、先生も、皆が私のことを「泣き虫」だと思っているに違いないと感じていました。
ある年のイースター(イエス・キリストの復活をお祝いするキリスト教の祝日)でのこと、ある子からイースターバスケットのプレンゼントをいただきました。で、そこに添えられた手紙に「あなたはイケメンなんだから、そんなに泣いてちゃダメよ」とつづられていました。
それは照れくさくもありましたが、それ以上にゾッとしました。それから数年経ち、私はバスケットボールチームに参加できる年齢に達しましたが、シーズンを乗り切れるわけがありません。試合の帰り道に泣き、一度はベンチでも泣きました。その日、スタンドにいる母に、「もうチームを辞める」と合図しました。そうしてその週のうちに、コーチへ「辞めたい」と伝え、そこでも泣いてしました。さらに、その夏の卒業パーティーでコーチとバッタリ会ったときにも泣いてしまいました。
そんな風に泣き虫のまま、17年間を過ごしたわけです。
現在も、相変わらず泣いています。最近の例としては、9.11アメリカ同時多発テロで双子の兄弟を亡くした女性に関する記事を読んだときのことです。またその前日、職場で嫌な会議があって、そこでも恐怖心でいっぱいになって数秒間泣いてしまいました。泣く時間は短かかったのですが、カリブ海を通過する嵐のように激しかったのは確かです。それはまるで、ちょっと長いくしゃみのしたような感じでした。
最近では、パソコンの前で起こることが多くなりました。頭を抱えて変な声を上げるものの、Tシャツで顔を拭ったら次のメールが来る前にはその緊張も解けています。
ですが2021年の6月初め、私は久しぶりに長時間泣いてしまいました。現在の婚約者であるキャサリンに求婚した後のことでした。翌週末を彼女の家族と1週間過ごし、クルマで帰宅する途中のこと。私は長年自分を蝕(むしば)んでいる、この「泣き虫」である事実を告白したときのことです。
私は一人っ子ですが、キャサリンは4人兄弟です。彼女の長兄は結婚しており、3人の子持ちでロンドンに住んでいます。3年間の付き合いの中で、私は彼女が姪や甥に夢中になっているのを「えらいなぁ」と讃えながら眺めていました。ビデオ通話やシェアされたたくさんの写真の中の可愛くて素晴らしい小さな子どもたちを、私は彼女の肩越しに眺め、私もその子どもたちが好きになりました。ですが、彼らから電話がかかってくるたびに、私は複雑な気持ちになっていたことは確かです。
彼女の他の兄弟にはまだ子どもがいなかったので、この3人の小さな人たちが、キャサリンの家族の中心でした。一方で、私の中心には自分自身しかいませんでした。私には3人の義姉妹がいて、それぞれに2人の子どもがいます。その子どもたちのことは確かに好きです。でも、キャサリンほど常にビデオ通話をし、共有アルバムがいっぱいになるほどの熱心さはありません。そうしてそのことが、私を悩ませていたのです。
私は、キャサリンや大抵の人々が持っているであろう「自分の家族を持ちたい」という情熱を持ち合わせていなかったのです。
このことはセラピーでも、両親に対しても、誰にも話したことはありませんでしたが、心の奥底で自分は「将来父親になりたい」という思いが強くないこと、ましてや"熱心に関わる叔父"になれるとは思えないことに不安を感じていました。
私は折に触れ、既に父親になった友人や父親になることを望んでいる友人に、このことについて訊(き)いてみました。私はそれを、まだ若く、自分の人生を生き、キャリアを積みたいということを理由にしました。
「子どもが欲しいかどうかわからない」という考えは、多くの人が理解してくれることでもあり、誰もが一時的に感じることなので。想像を絶するような発言ではありません。
ですが、正直なところ、「子どもを欲しくないのか?」と正面切って言われると、全く確信が持てないのです。私は自分自身よりも小さな子どもを優先して、自分のエネルギーを捧げられるほど、「自分の子どもが欲しい」という気持ちは高ぶっていなかったのです。そんな自分について、悩んでもいました。
私は常に、不安を抱えて毎日を過ごしています。そうして毎日を乗り切り、パートナーや両親、同僚など周囲の人たちとやっていくのに、全力を尽くすことで精一杯なのです。
私が自分に課した理想は、「他の人からその存在を感謝される人間になる」ということ。そのことで、私の精神的エネルギーのすべてを注いでいたと言っていいでしょう。でも、その考えを維持することは大変なことでした。うまくいっていると思えないことも多々ありました。自分の子どもができ、その子と公園で過ごす時間や夜泣きに気を取られている時間となれば、「僕の理想を維持することは難しいから」と思っていたのです。
母が父(当時はまだ恋人)に「妊娠したかもしれない」と告げたとき、父の反応は 「妊娠しているといいね!」というものだったそうです。それから2人は宝石店へ行き、父は片膝をついてプロポーズしたそうです。
私はいつも両親を尊敬していました。私という存在によって、思いがけずすべてが変わってしまう可能性があるにもかかわらず、それをポジティブに捉え突き進んできたのです。ただ両親は、私以外に子どもを持たなかったので、私には弟も妹もいません。
「その代わり」と言ってはなんですが、私の両親には子どものいる兄弟がいました。実のところたくさんいました。私はいとこたちのことを、「一緒に育った兄弟姉妹だ」と話す一人っ子だったのです。そう実感していたのも確かです。

かつて友人の家のリビングに立ち、廊下に飾られている家族写真をうらやましく思ったことがあります。結婚式や記念日、甥や姪、孫など、みんなが見られるように飾られた絆の固いひとつのチームです。私は今でも、そうした家族構成をうらやましく思っています。ですが、家族を持ち、それを永遠に管理する覚悟を決めるという意識的な決断は結局のところ、他人事にすぎませんでした。私はそのショーを、最前列で観たいという思いはなかったのです。そしてそんな自分を、「何か異質な人間なのでは?」と感じてもいたのです。そんな私から見た他の人たちは、私自身がまだトレーニングにも入っていないレースで、数周先を行っているような存在に見えていました。
同僚であり友人でもある人が、「そうなってみるまでは、準備ができているかどうかなんてわからなかった」と言っていたことがあります。また、生まれたばかりの子どもの目を初めて見たときに起こる感動的な現象についても、聞いたことがあります。私は「そのときを待つんだ」と自分自身に言い聞かせていました。そんなプロセスに委ね、成り行きに任せる、といった感じです。きっと、そのときは来るはずです。ですが、そんな思いを自分自身で再確認した後でも、また子どもたちとビデオ通話をすることになると、私は罪悪感と焦りに苛まれることになったのです。
彼女のお母さんのビーチハウスで婚約した翌週、キャサリンと私は、自分たちだけでお祝いをした後、クルマで海岸に戻りました。その後、彼女の義理の姉と3人の小さな子どもたちもロンドンからやって来る予定でした。私たちが到着してからの1分1秒は、彼らの到着を心待ちにしていました。私はその週末、彼らが水泳のレッスンを受けたり、砂の城をつくったりするのを見るのが楽しみでした。とは言え、この子たちはもはや他人のようには感じられなくなったものの、まだ"誰か"の子どもであり、"誰か"の姪っ子や甥っ子という存在でした。
それに私は、子どもたちが夕食前にミミズ型グミを食べていいのか? 寝る前に「ダークウイング・ダック」のエピソードをもう1回見ていいのか? などの決定を出せるような立場でもありませんでした。私はただ彼らの両親や、叔母の決定に従っているだけだったのです。
それが一変するときを迎えました。それは彼らと合流してから、15分も経たないうちのことです。
その日の午後、キャサリンの4歳の甥が歩いてきて、私に質問をしました。何を訊きたかったのかは覚えていません。ですが彼は、「ベンおじさん!」とすべてを変える言葉を前置きして質問してきたのです。
私は「はい」と答えたか、すぐに彼の質問に答えたか、彼が「ヘイ、ミスター!」と言ったときと同じ反応をしたか、このうちのいずれかだったと思いますが、私の心には今までなかった感情が芽生えたのです。キャサリンもその場にいて、それを聞いて、それがどんな意味を含んでいたかを理解してくれました。
その子が立ち去ったとき、私たちはお互いに顔を見合わせました。そして彼女の顔は、「ワオ!」と言っているのです。私の顔は 、「何てことだ!」と言う感じだったと思います。
「姉がクルマの中で、子どもたちに話したに違いないわ」とキャサリンは言いました。「私たちが婚約したことで、私はもうただのベンではなくなり、子どもたちは私に適切な称号を与えることを許されたのではないか?」と、私たちは推測しました。
そうです、私はついに正式に「ベンおじさん」になったのです。
この1週間、そして今現在も…。私は、甥ができたことの喜びを感じるようになった、と言っていいでしょう。もう一人の甥は、キャサリンに抱かれて自分の部屋へ向かうとき、廊下の曲がり角で微笑んでいるのが見えました。そして姪は、後になってですが、私を「ベンおじさん」と呼ぶようにもなりました。甥のほうはこの1週間、私の脛(すね)や肩にしがみつくようになりました。
私はその子らの水泳のレッスンを見たり、猫のピートと遊んだりもしました。私の足下にあった卵の殻はもうそこにはなく(もう生まれたてのひよっこではなく)、私は彼らのおじさんになれたのです。
正式なおじさんとなれば、彼らにお菓子をこっそり与えても、そこに迷いを感じる必要もありません。正式なおじさんなら、甥たちにボードゲームでの不正行為がなぜ報われないのか?を教えてあげることもできるのです。少々の迷いもありながらも、私は乗り出す勇気を得たのです。
この機会が、私自身の最初のレッスンとなったのです。 そして、姪と1週間過ごした後、彼女は私に「愛している」とまで言ってくれました。いつか彼女が理解できるようになったら、「その言葉が私にとってどれほど意味のあるものだったか」を伝えたいと思います。
前述の、甥が「おじさん」と初めて言ったときにそろって反応したエピソードの後、キャサリンと私はその後のことについて、あまり話していませんでした。ですが私自身は、その後のことについて考えずにはいられませんでした。
「おじさん」発言の翌朝、私は目覚まし時計が鳴る3分前に、ベッドの足元でおもちゃの鉄砲の弾を込める音で起こされました。目覚めたとき、私は武装して笑う2人の幼児の銃身を見つめていました。私は携帯電話を手に取り、写真を撮って、インスタグラムのストーリーに投稿しました。リアクションのひとつに、私は「#おじさんの生活(#unclelife)」というハッシュタグを付け、嬉々(きき)として投稿しました。この陳腐な言葉は、私に「ダサい」と思わせるものではなく、何か新しくも愛おしいものの一部だと感じさせてくれたのです。
その週の終わり、帰り道でキャサリンに話をしました。まだ、その地区の外にも出ていないのに運転しながら、久しぶりに長く泣いてしまいました。
一息ついてから、私は彼女に、初日からのこの些細な悩みに私が追い詰められていたことを話しました。ここに書いたことのほとんど、つまり、胸のつかえや私が苛まれていた罪悪感について話したのです。ですが、「おじさん」の一言で、その後の1週間は重荷を下ろしたというよりも、新しい生活の始まりのように感じられるようになったことも。
私は、子どもを持つことに無関心な人を責めるつもりはありません。できるわけがありません。ただ、いま私の(子どもを持つことに対する)無関心さは消えてしまったのです。
甥たちのおかげで、「物事は一瞬にして変わり得る」ということを知りました。そしてさらに、「自分の子どもを持つ」ことが明らかになる瞬間を楽しみにできるようになったのです。ベルクロで開閉する靴を履いた幼児たちに、この苦境から抜け出させてもらえるとは思ってもいませんでした。ですが、そうなったのです。正式な「おじさん」になったことで、私は自分がその存在を知らなかったプロセスのステップを見つけることができたのです。
そして、これが私なのです。この1週間、そして今現在…。私は正式な「ベンおじさん」なのです。そうです、もう、ただの「ベンおじさん」じゃないのです。そうして私はついに、「希望に満ちた熱心な父親になりたい」と思えるようになったわけです。
今でも、「自分に弟や妹、家族ができることはどんなものか?」に関しては、まだ具体的にはよくわかりません。ですが、私はもう自分が特殊な人間だとは思わないようになりました。そして今では、寂しさを感じることもずいぶん減りました。
Source / ESQUIRE USTranslation / Keiko Tanaka※この翻訳は抄訳です。
Related StoriesカミングアウトしたLGBTQ+の子どもに対して、親がとるべきサポート方法とは? 冒険心にあふれた子ども(そして自分自身も)に育てる秘訣大人も楽しめるおもちゃで、おうち時間を子どもと楽しもう。This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io